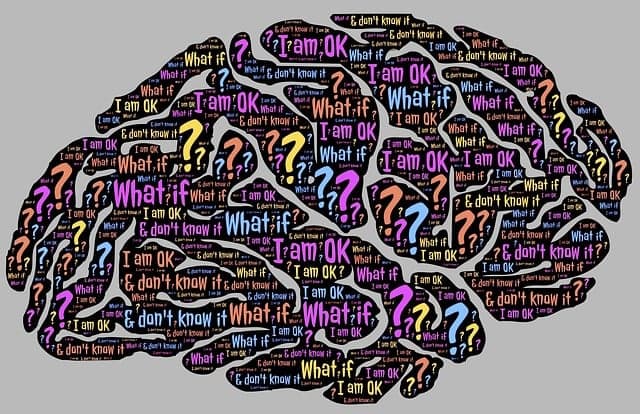
ブログランキング参加中☟
株を買う時とスーパーの買い物で異なる金銭感覚

株式投資を始めた当初は最小単元で買い入れるだけでもかなり緊張したのを覚えています。
その後、2020年にコロナショックで株価が暴落した際、1,500万円以上(当時の保有資産の大半)を数か月のあいだに株式へと変換しました。
いま思えばその経験がきっかけとなり、金銭感覚がダブルスタンダード化したように思うのです。
株を買う場合はたいてい10万円以上(場合によっては数百万円)を一度に使う訳ですが、その時の心理的負荷とスーパーで50円高い牛乳を買う時の心理的負荷が同じくらいなんじゃないかということにふと気づきました。
投資はお金を増やすための行為。食品は消費行動。

あたりまえですが、株式投資はお金を増やすための行為です。
誰しもお金が減る前提で株を買う訳ではないので、大きな金額の投資でも心理的負荷は少ないのかもしれません。
一方、食品や日用品は一度買ったらカラダへの栄養やモノとしての価値は残りますが使ったお金は二度と戻ってきません。
このあたりの違いが同じお金を使う行為であっても心理的負荷を感じる金額に大きな差が生じる要因なのかもしれません。
おわりに|投資関係は鈍感、でも消費行動は敏感でいたい

株式投資は通常、売買を行う前の段階で投資先の情報を吟味してお金を動かします。
そのため買い付けに投じる金額の多寡にかかわらず淡々と計画を実施すべきと考えます。
一方で、スーパーでの買い物などではいつまでも金銭感覚に敏感でいたいと思うのです。
1円でも安いお店を探して店舗をはしごしましょう!なんてことを勧める訳ではありません。
ただ、同じ牛乳でも130円と200円の商品があるとき、そこに50円分の価値があるのか?くらいの好奇心は持ち続けたいですね。
株式投資の運用額がある程度まとまった額になると、日々の変動額が軽く月給を超えることもあります。
また、配当金もまとまった額になってきて小さな金額の差を気にしなくなることも。
それでも、私のようなただのサラリーマンがこれまで築いてきた資産はこのような些細な好奇心と気づきを取りこぼさずに吟味したからこそあるのだということを忘れてはいけないと感じています。
とりとめのない記事になりましたが株式投資家として金銭感覚がダブルスタンダード化しているというお話でした。
投資では損益額を気にしすぎない
日常モードでは些細な金額差でも気に留める
では、また。
応援よろしくお願いします☟



コメント